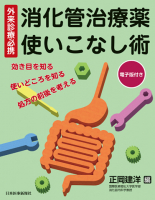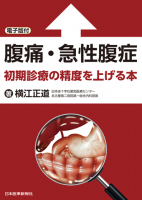お知らせ
炎症性腸疾患と再生医療 【再生医療による炎症性腸疾患の難治性潰瘍治療への応用が急速に発展・普及している】
炎症性腸疾患は消化管に原因不明の慢性炎症を起こす難病として知られ,炎症をいかに制御して「寛解」を維持するか,という点が最も重視されてきた。しかしながら,抗TNF-α製剤などの生物学的製剤の登場により炎症の制御は格段の進歩を遂げ,きわめて良好な寛解状態を長期的に得られることもめずらしくなくなってきた。一方,本疾患の病因・予後決定の重要な要素として「正常な粘膜上皮機能」が注目され,炎症の制御に加えて損傷した粘膜上皮の再生を指す「粘膜治癒」が重要な治療目標として国際的にも共有されている。
難治性の潰瘍が残存し「粘膜治癒」が得られない症例に対する新しい治療として,組織幹細胞を用いた「再生医療」に期待が集まっている。「間葉系幹細胞」は腸管・骨髄・脂肪組織などに内在する「間葉系」への多分化能を保持した幹細胞であるが,異なる個体・組織に移植をしても免疫学的な拒絶を受けにくく,かつ抗炎症・組織再生効果を発揮することから,炎症性腸疾患を含む様々な疾患に対して移植治療の臨床試験が実施されている。
一方,これまで腸上皮幹細胞を体外で培養することは不可能であったが,わが国の研究者らが開発した「腸上皮幹細胞をオルガノイドとして培養する技術」を発端として急速に発展・普及しており,これを炎症粘膜に移植・定着させうることも実験的に示されている。これらの技術を炎症性腸疾患の難治性潰瘍に応用するための治療法の開発は,iPS細胞の実用化と並んでわが国の再生医療プロジェクトのひとつとして進められている。