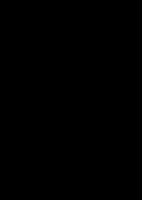お知らせ
(4)肥満症患者への適切な心理的アプローチ ─臨床心理士の立場から [特集:現在の肥満症治療のあり方]

肥満症治療において認知行動療法(CBT)の技法を導入する際には,患者の心理学的特性を把握し,協同的な治療者-患者関係を築いておくことが重要である
J. Beckの認知療法に基づくダイエットプログラムが開発されている

臨床心理士はチーム医療において治療をうまく進めるための潤滑油的な役割を担うことができる
1. 認知行動療法(CBT)の動向と注意点
当科では,医師,看護師,栄養士らのチーム医療において,認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy:CBT)を基本としたオリエンテーションがあり,そのスキルを持った臨床心理士も参加している。肥満症治療に対するCBTはCooper&Fairburnら1)のプログラムが有名で,既に多くの施設で実践されている。また,最近では,認知療法の大家であるJ. Beck2)が肥満症患者特有の「言い訳思考」に着目したダイエットプログラムを提唱している。特に前者に関しては,臨床心理士のいない施設でも様々な医療スタッフによって実施されており,その報告が学会などで多く発表されている。
一方で,なかなかCBTプログラムに乗らない患者や,中途での脱落に対する苦悩も耳にすることが多いように思う。この点に関しては,CBTが疾患特異的な介入技法を多く持つがため,技法ありきの導入になってしまいがちなことが影響しているのではないかと考えている。現在も様々な介入技法が研究開発されているが,その実,うまく導入・活用するためにはほかの心理療法と同様,個々の症例に合わせてカスタマイズするための心理社会的な症例理解のプロセスが必須である。そして,この部分が臨床心理士の得意とする部分である。
便宜的に本稿では,症例理解のための理論・技法を広義のCBT,肥満症治療のための介入技法を狭義のCBTとする。そして,今後,肥満症患者の治療に関わるであろう医師の先生方が介入技法をうまく導入・活用するためのコツとして,前者を中心に解説する。
2. 肥満症患者の心理学的特性─性格傾向,心理状態,IQ・認知機能について
海外の論文では,性格特性5因子モデルを用いた肥満症患者の性格傾向研究に関してメタ解析を行い,「誠実性」(コンピテンス,秩序,良心性,達成追求,自己鍛錬,慎重さ)が低いことが肥満症のリスクと関連すると報告されている3)。それに対し,性格特性5因子モデルを用いて肥満症患者と一般成人における性格傾向の違いを検討したわが国の報告では,両群間に統計的差異は認められなかった4)。しかし,肥満症患者群においては,肥満度が高い患者ほど神経症傾向(特に不安と抑うつ)が高く,感情同定困難な特徴が認められた。このことから,海外で用いられた心理療法のプロトコールをそのまま流用するのではなく,目の前の患者の心理学的特性に合わせてカスタマイズしていくことが好ましいと考えられる。またわが国においては,肥満度が高い患者ほど,心理的アプローチが重要になる可能性があると心にとめておくとよいかもしれない。
性格傾向以外では,IQの低さが間接的に肥満と関連していることもコホート調査にて報告されている5)。これらの問題も介入に先立ち把握しておくとよい。
最近,一見すると通常の患者のようだが,一部の認知機能が特異的に低下(たとえば言語的な理解力は平均的なのに,視覚的理解力に難がある場合は通常の診察やカウンセリングでは気づきにくい)しており,適応的な行動がとりにくい患者と出会うことが少なくない。このような場合,治療への動機づけ,脱落防止には認知機能の特徴に沿った工夫が必要である。このような患者の特徴はWAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale)-Ⅲなどの神経心理学検査で把握することができるが,これは臨床心理士の得意とする分野のひとつである。
また経験的に,肥満症の罹患歴の長い患者は,自己流ダイエットや医学的治療の挫折経験を持っていることが少なくない。患者は学習性無力感と称される「どうせ,何をやったって無駄だ」という想いを抱いていることがある。肥満症の患者と向き合うときには,彼らの自尊心と希望を丁寧に引き上げることが重要なときがあると言える。

残り4,499文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する