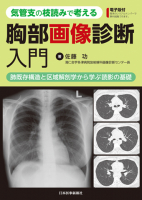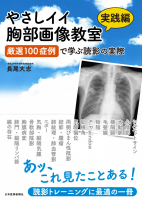お知らせ
(1)かかりつけ医が知っておくべき薬剤性肺障害のトピックス [特集:新規薬剤が引き起こす薬剤性肺障害]

あらゆる薬剤が肺障害を誘発する
薬剤性肺障害の実態把握には多くの使用実績が必要である

薬剤性肺障害の治療原則は被疑薬の中止であるが,例外的な対応が必要な薬剤も出てきている
1. あらゆる薬剤が肺障害を誘発する
薬剤性肺障害の報告件数から推定すると,おそらく最も多い原因薬剤は抗悪性腫瘍薬であり,そのほか,抗リウマチ薬,抗菌薬,漢方薬などが挙げられる1)。抗リウマチ薬では,関節リウマチ治療の中心となり“アンカードラッグ”と位置づけられているメトトレキサート(methotrexate:MTX)が肺障害を起こすことはよく知られており,後述するレフルノミドやブシラミンなどの抗リウマチ薬なども肺障害を起こすことが知られている。漢方薬は多種の製剤が臨床で使用されるが,漢方薬の副作用報告の解析から,副作用1958件中406件が間質性肺疾患であったとの報告もあり2),漢方薬による薬剤性肺障害は想像以上によくみられる副作用と言えるかもしれない。
そのほか,潰瘍性大腸炎に使用されるメサラジン,抗不整脈薬のアミオダロンなどもしばしば肺障害を経験する。また,稀ではあるが,ロキソプロフェン3),シンバスタチン4)などの消炎鎮痛薬やHMG-CoA還元酵素(hydroxymethylglutaryl-CoA reductase)阻害薬といった日常診療で頻用される薬剤でも肺障害の報告がある。
このように,薬剤性肺障害はあらゆる薬剤により誘発する可能性があり,幅広い領域で起こりうる副作用である。臨床医は,薬剤性肺障害にいつ遭遇してもおかしくないということを念頭に置く必要がある。

残り5,365文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する