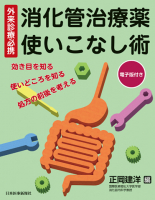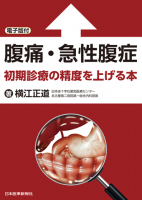お知らせ
(2)診断能向上につながる10のポイント [特集:消化管疾患はエコーで診断する]

系統的走査法により得られた超音波画像解析においては,パターン的な診断をすることなく,先入観を持たずに画像から得られるすべての情報を収集し,10のポイントに従って解析しながら,その背景に存在する病態を推測・把握していくことが診断能向上につながる
1. 消化管の壁構造と超音波像
一般に,胃や腸の正常壁構造は,内腔から5層のエコーレベルに分離描出され(図1),組織との対比もほぼコンセンサスが得られている。すなわち,粘膜面より第1層の高エコー(①内腔と粘膜表面の境界エコー),第2層の低エコー(②粘膜筋板を含む粘膜層),第3層の高エコー(③粘膜下層),第4層の低エコー(④固有筋層),第5層の高エコー(⑤漿膜と境界エコー)の5層構造として描出される。また,層構造の判読ポイントとして,5層構造に明瞭な描出ができない場合でも,粘膜下層の高エコー帯が明瞭に認められれば,層構造は温存されていると判断してよい。


2. 画像解析における10のポイント
消化管疾患の超音波診断に際しては,まず基本となる系統的走査法を活用し,病変部位・罹患範囲を同定することが診断への第一歩である。すなわち,胃,十二指腸,小腸(上中部,下部),大腸(右側~左側結腸,直腸)のいずれかの部位に病変が局在するかを同定し,腸管壁の肥厚・拡張の判別,罹患範囲,経時的変化などを観察する。さらに正確な画像解析を行うことにより,多種多様な消化管疾患に挑むことができる。筆者が代表幹事を務める消化管エコー研究会(代表:川崎医科大学・畠 二郎教授)により提唱されている「診断に役立つ10のポイント」を表1に列挙する。実際には,これらを総合的に判断して超音波診断を決定している。


残り2,681文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する