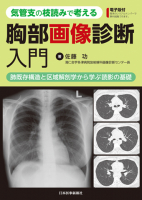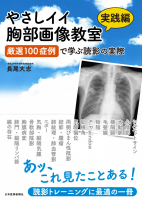お知らせ
(3)欧米における肺癌サバイバーシップの現状[特集:肺癌サバイバーに医師ができること]
がんサバイバーシップとは,患者の不安,経済的困難,就学・就労・結婚・出産・育児などの問題を,家族・友人・医療者,地域社会全体で支え合っていくことである
がんアドボカシーとは,がん患者を国や自治体,医療従事者,ボランティア団体などが支援する活動を指し,各々の立場で行動目標や活動計画を立てて実施するものである

米国疾病対策センター(CDC)による総合的ながん対策や,英国におけるがん患者中心のアドボカシー団体であるAPPGC(がんに関する超党派議員連盟)による政策,カナダの「がん対策キャンペーン」によるがん対策意識の普及推進などの事例があるが,いずれもがん専門医がアドバイザーとして医学的側面から支えている
1. がんサバイバーシップとがんアドボカシーの意味と歴史
がんサバイバーシップとは,がんと診断された患者が合併症や再発への不安,経済的困難,人間関係,就学・就労・結婚・出産・育児など私生活に関する諸問題など直面する課題を,周囲の家族・友人・医療従事者そして地域や社会全体で支え合っていくことである。一方,がんアドボカシーは,がんサバイバーを困難や課題を抱えた対象ととらえ,国や自治体,医学会,ボランティア団体などが支援する活動を指し,各々の立場で行動目標や活動計画を立てて実施するものである。
したがって,医師や医療チームが,受け持ちの肺癌患者や家族を支えていくことは,肺癌サバイバーシップであり,日本肺癌学会や世界肺癌学会(The International Association for the Study of Lung Cancer:IASLC)が行っている肺癌患者支援活動は,がんアドボカシーと呼ばれる。
このような社会的弱者への支援は,英国において産業革命を経て始まった。その代表的な例がセツルメント運動である。これは,持つ者と持たない者がともに相集って一定の地域,場所で共同して支え合う精神に基づくボランティア運動で,近代の社会福祉,ソーシャルワークの形成・発展の礎となった。記述に残されているものとしては,1884年にバーネット牧師夫妻が設立した英国のトインビー・ホールが世界最初とされるが,諸説ある。
一方,米国ではジェーン・アダムズらが1889年に開設したハルハウスが広く知られている。
わが国でも,1921年に設立された大阪北市民館など公設のセツルメントや,同年に始まった東京下町における東大新人会の学生による低所得者層への様々な活動がある。戦後も医学部のサークル活動の一環として,医学生や看護学生の中にセツルメント運動に参加するものがあり,医師や看護師となってからも様々な患者支援など社会活動に取り組むものが現れた。
世界恐慌,第二次世界大戦を経て,欧州,米国では経済的混乱や戦争不安が落ち着き,医療の進歩は,がんの診断と治療(当時は,ほとんどが手術治療であった)において目覚ましいものがあり,その結果,がんサバイバーの直面する課題が議論されるようになった。
文献上,最初のがんサバイバーシップの記述は,Mullan Fitzhughによる“Seasons of survival:reflections of a physician with cancer”という論文で,くしくも縦隔胚細胞腫であった医師のMullanが,生存率の向上を目指すだけの医師を非難し,治療プロセスの重要性を述べている。Mullanは1986年にNational Coalition for Cancer Survivorshipを設立し,初代会長に就任している。
他方,がんアドボカシーの始まりは,元米国大統領ドナルド・レーガン夫人,ナンシー・デイビス・レーガンと言われる。ナンシーは,カリフォルニア州知事夫人として,退役軍人,高齢者や障害者の元を訪れ,多数の慈善団体とともに活動し,その慈善活動をフォスター・グランドペアレント・プログラムとともに始めた。大統領夫人となってからも継続する中,1987年10月に乳癌となったが,乳房切除手術を受け回復した。このことで乳癌に対する意識が全米に広まり,ナンシーの慈善活動と相まってがん対策やがんアドボカシーが認知され,政策に反映されたと言われる。