お知らせ
上室期外収縮[私の治療]
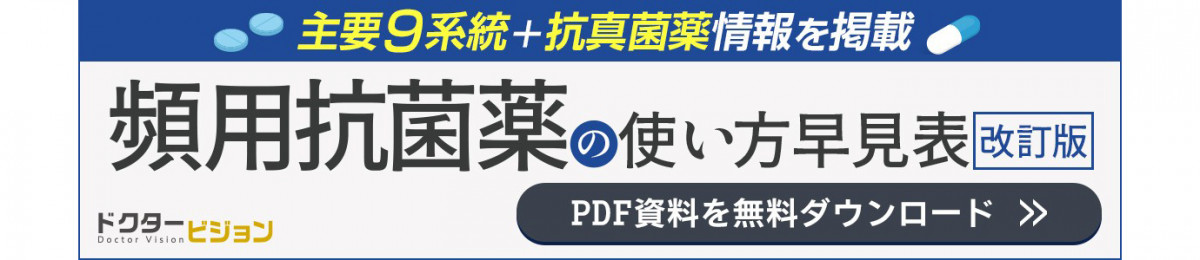
上室期外収縮とは,洞調律時に上室由来の異所性興奮波が早期に出現するものである。心房期外収縮と房室接合部期外収縮にわけられるが,ほとんどが心房期外収縮であるため,上室期外収縮≒心房期外収縮として認識されている。単発性あるいは連発性で出現する。ありふれた不整脈であり,心疾患を有する患者のみならず,健常者においても出現する。自律神経活動の影響を受けやすく,ストレス,過労,睡眠不足に加え,飲酒,喫煙などでも増加する。良性の不整脈である。
▶診断のポイント
【症状】
発現初期には,動悸や脈がとぶ/脈が抜けるといった心拍の結滞感を自覚する。しかし,ある程度経過した患者においては無症状なことが多い。

【検査】
頻発している患者では12誘導心電図で診断できるが,散発性に出現する場合は,ホルター心電図やイベント心電図などの携帯型心電図で診断する。運動で出現する場合には運動負荷心電図を考慮する。心房細動に進展することがあるので,定期的に心電図検査を行う。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
以前は,不整脈を消失あるいは減少させることに重点が置かれてきた。そのため,多くの抗不整脈薬やデバイスが開発され使用されてきたという歴史がある。しかし,今日では患者の症状と生活の質(QOL),そして生命予後の改善に重点が置かれるようになった。
上室期外収縮は良性の不整脈であるため,頻発していても症状が乏しく,QOLを損ねていなければ治療は行われない。逆に,症状が強く,QOLを損ねており,日々の活動に支障をきたしていれば治療を考慮する。
治療を行う場合には薬物治療が選択される。主にⅠ群抗不整脈薬(Naチャネル遮断薬)とβ遮断薬が使用される。ただし,Naチャネル遮断薬は心機能低下例では使用できない。経過中に心房細動に進展することがあるが,その傾向がみられた場合は心房細動の治療法に準じる。

残り998文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する













































