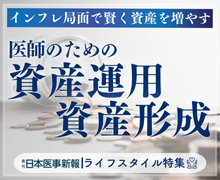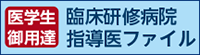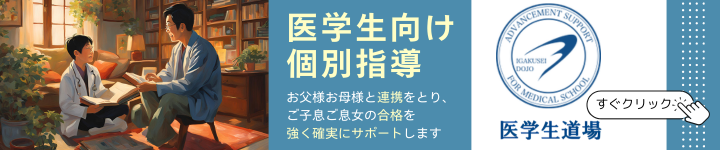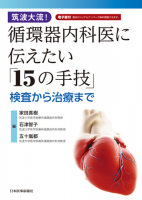お知らせ
拘束型心筋症[私の治療]
拘束型心筋症は特発性心筋症のうち,心筋の肥大や心室の拡張を伴わないものの,拡張機能障害により心不全症状を呈する。比較的稀な疾患であり,正確な疫学統計に乏しいが,2002年のデータで全国の患者総数が300人という。おそらく若年者に多い。特定の遺伝子変異との関連は知られていないが,家族歴を有する例は少なくなく,遺伝的素因により発症すると考えられる。
▶診断のポイント
【症状】
心不全症状として,呼吸困難・動悸・易疲労感・胸痛などを生じる。

【身体所見】
頸静脈怒張(時にKussmaul徴候)・下腿浮腫・肝腫大・腹水などを認めることがある。奇脈はほとんどない。聴診上,Ⅲ音や収縮期雑音(僧帽弁逆流・三尖弁逆流)などを認めることがある。
【検査所見】
心電図は心房細動・上室性期外収縮・低電位差・心房/心室肥大・非特異的ST-T異常・脚ブロックなどを認めることがある。心エコー図では,心拡大の欠如と正常に近い心機能により拡張型心筋症との鑑別,心肥大の欠如により肥大型心筋症との鑑別を行う。心房拡大・心腔内血栓・房室弁口流入波高の呼吸性変動<25%などを認めることがある。心臓カテーテル検査で,冠動脈造影において有意な冠動脈狭窄を認めず,左室造影では正常に近い左室駆出分画を呈する。右心カテーテル検査による左室優位の心室拡張機能障害が,特徴的な所見である(右房圧と肺動脈楔入圧の上昇およびW型波形,左室と右室の拡張末期圧上昇とdip and plateaux波形,肺動脈収縮期圧>50mmHg,左室拡張末期圧>右室拡張末期圧+5mmHg)。心内膜下心筋生検で特異的な所見はないが,心筋間質の線維化,心内膜肥厚などを認めることがある。
【除外診断】
鑑別診断するべき疾病は,収縮性心膜炎,虚血性心疾患,高血圧性心疾患,肥大型心筋症,拡張型心筋症,二次性心筋症(心アミロイドーシス,心サルコイドーシス,心ヘモクロマトーシス,グリコーゲン蓄積症,放射線心筋障害,家族性神経筋疾患),心内膜心筋線維症。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
拘束型心筋症の確立された治療はない。利尿薬による症状緩和がメインである。重症例においては心臓移植の適応を検討する。植込み型補助人工心臓の適応となる場合もあるが,一般的ではない。心臓移植待機中に静注強心薬依存となる場合,肺血管抵抗を軽減させるPDE-Ⅲ阻害薬を使用することがある。

残り1,292文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する