お知らせ
【文献 pick up】心房細動例への第Xa因子阻害薬と間質性肺炎リスク:台湾大規模解析
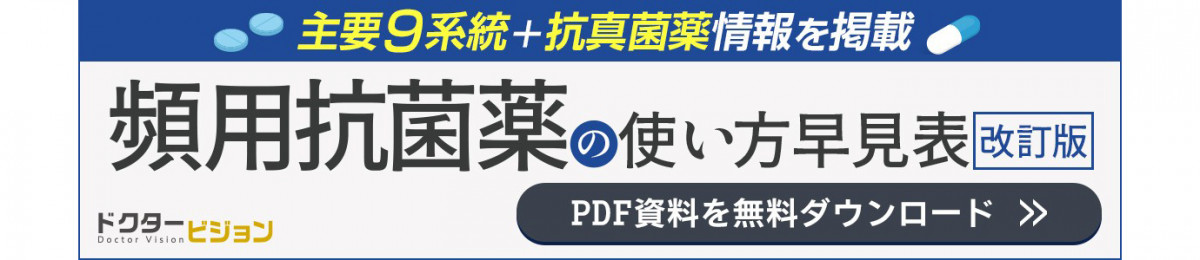
心房細動(AF)例の脳梗塞・塞栓症抑制において標準薬となった直接経口抗凝固薬(DOAC)だが、米国の自主的報告有害事象システム(FAERS)解析から間質性肺炎リスク上昇の可能性が報告され、特にアジア人における頻発が示唆された[Raschi E, et al. 2020]。
そこでアジア人DOAC服用例における間質性肺炎リスクを評価すべく、台湾・長庚紀念病院のYi-Hsin Chan氏らは自国データベースを用いた解析を実施。11月22日、JAMA Netw Open誌に報告した。

第Xa因子阻害薬ではワルファリンに比べ間質性肺炎リスクは有意に上昇するが、薬剤変更を考慮する必要はないとの結論だった。
同氏らが解析対象としたのは、台湾の公的保険データベースから抽出された、経口抗凝固薬(OAC)の処方があった非弁膜症性AF 1万6044例である。AF以外にOACの適応がある例、あるいは慢性肺疾患既往例、末期腎不全例などは除外されている。
平均年齢は73.4歳、男性が56.6%を占めた。OACの内訳は、60.9%が第Xa因子阻害薬、21.2%が直接トロンビン阻害薬、17.9%がワルファリンだった。
これら1万6044例で間質性肺炎初発診断の有無を確認し、第Xa因子阻害薬群、直接トロンビン阻害薬群、ワルファリン群間で比較した。
比較にあたっては傾向スコアを用いた調節を行い(傾向スコア安定化重みづけ)、背景因子には、年齢、性別、脳梗塞や大出血リスク、合併症、併用薬剤などを含め有意な群間差はなかった。
その結果、2012年から19年までの間の間質性肺炎発症率は、第Xa因子阻害薬群0.29/100例・年、ワルファリン群0.17/100例・年となり、ハザード比(HR)は第Xa因子阻害薬群で有意に高値となっていた(1.54、95%信頼区間[CI]:1.22-1.94)。ただし絶対リスク差は小さいため(0.12/100例・年)、NNH(Number Needed to Harm)は834例/年となる。
また第Xa因子阻害薬を個別に比較しても(アピキサバン、エドキサバン、リバーロキサバン)、ワルファリンに比べた間質性肺炎リスクの有意上昇は共通していた。
第Xa因子阻害薬に伴うリスク上昇の機序は不明だという。
一方、直接トロンビン阻害薬では、ワルファリンに比べ間質性肺炎のリスク増加傾向は認めたものの、有意差には至らなかった(HR:1.26、95%CI:0.96-1.65)。
なお原著者らは、これらの結果は治療中AF例に対するDOACからワルファリンへの切り替えを推奨するものではないとした上で、この解析から必要性が明らかになったのは、DOAC服用例に対する肺機能と呼吸器症状・症候の注意深い観察だと考察している。
本解析は、長庚紀念病院から資金提供を受けて実施された。













































