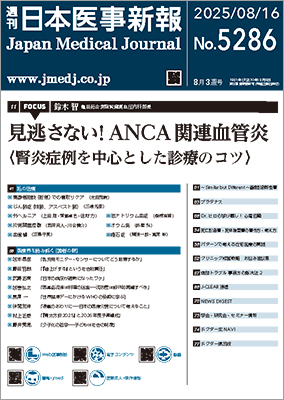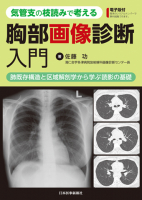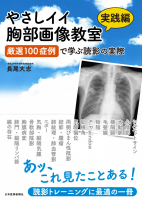お知らせ
小細胞肺癌[私の治療]

小細胞肺癌は肺癌全体の約10~15%を占めるがんであり,増殖速度が速く早期にリンパ節転移や遠隔転移を認める悪性度の高い腫瘍であるが,放射線治療や薬物療法に対する感受性が高いことが特徴である。
▶診断のポイント
【症状】
呼吸困難感,咳嗽,血痰などが挙げられる。

【検査所見】
肺門部型肺癌が多く,喀痰細胞診断や気管支鏡検査が有用となる場合が多い。
腫瘍マーカーとしてProGRPやNSEが挙げられ,陽性率はそれぞれ約60%,約70%とされる。組織検体では,N/C比の高い小型細胞で,細胞質は乏しく広範な壊死背景を伴う腫瘍細胞が典型的で,免疫組織化学染色ではCD56,chromogranin A,synaptophysinなどが陽性となる。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
当院では,基本的にはシスプラチンの選択を考慮するが,高齢者や腎機能低下例(クレアチニンクリアランス<60mL/分)では,カルボプラチンを選択している。
間質性肺疾患合併例の治療では,カルボプラチン+エトポシドの安全性が比較的高いとされている1)。二次治療以降では前向きエビデンスがないことから患者と相談の上,治療方針を決定している。また,免疫チェックポイント阻害薬の使用の可否については,非小細胞肺癌のエビデンスにはなるが,蜂巣肺,拘束性肺障害,自己抗体がないことを確認している2)。
免疫チェックポイント阻害薬の選択について,アテゾリズマブとデュルバルマブが適応となっているが,いずれの薬剤も治療効果は類似している。薬価が低く,シスプラチンの使用機会が減少していることからも,個人的にはアテゾリズマブを使用することが多い。

残り1,485文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する