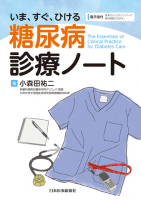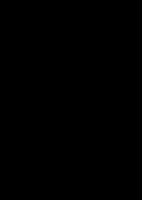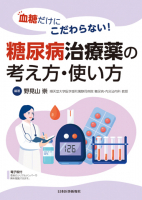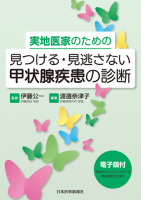お知らせ
副甲状腺機能亢進症[私の治療]

▶治療の実際
【外科手術】
腺腫の場合,罹患腺腫を摘出する。過形成の場合,副甲状腺全腺を摘出し,一部を前腕筋内などに自家移植する。副甲状腺癌の場合は,再発すると予後不良であり,完全切除を心がける。このため術中PTH迅速測定で確認する。
【内科的治療】
〈自覚症状がない場合〉
水分摂取と適切な運動を推奨し,Ca感知受容体作動薬の投与を検討する。骨粗鬆症には積極的に介入する。

一手目 :オルケディアⓇ2mg錠(エボカルセト)1回1錠1日1~2回(朝または朝・夕,食前または食後)
増量は2週間以上の間隔をあけて1段階ずつ行い,最大用量24mg(1回6mg 1日4回)まで。
二手目 :〈一手目に追加〉ボナロンⓇ35mg錠もしくはフォサマックⓇ35mg錠(アレンドロン酸ナトリウム)1回1錠 週1回(起床時),またはベネットⓇ75mg錠もしくはアクトネルⓇ75mg錠(リセドロン酸ナトリウム)1回1錠 月1回(起床時)
三手目 :〈処方変更〉ボノテオⓇ50mg錠もしくはリカルボンⓇ50mg錠(ミノドロン酸水和物)1回1錠4週に1回(起床時)
四手目 :〈処方変更〉ボンビバⓇ注シリンジ(イバンドロン酸ナトリウム水和物)1回1mg 月に1回(できるだけ緩徐に静注)
五手目 :〈処方変更〉リクラストⓇ注(ゾレドロン酸水和物)1回5mg 年に1回(15分以上かけて点滴静注)
六手目 :〈処方変更〉プラリアⓇ注(デノスマブ)1回60mg 6カ月に1回(皮下注)
デノタスⓇチュアブル配合錠(沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム)などのCa補給薬は併用しない。
〈自覚症状がある場合〉
消化器症状と多飲・多尿がある場合には,急速に状態が悪化する可能性があり,上記の骨粗鬆症に対する治療と並行して,高カルシウム血症に対する治療を行う。
一手目 :生理食塩水1000~2000mL/日(点滴静注)
脱水の程度や飲水量・全身状態を勘案して投与量を決定する。
二手目 :〈一手目に追加〉エルシトニンⓇ注(エルカトニン)1回40単位1日2回(生理食塩水100mLに稀釈し1~2時間かけて点滴静注)
筋注も可能であるが,通常は点滴静注する。アナフィラキシーショックに注意する。効果が減弱するため,2週間程度をめどに中止する。
三手目 :〈一手目に追加〉オルケディアⓇ2mg錠(エボカルセト)1回1錠1日1~2回(朝または朝・夕,食前または食後)
増量は2週間以上の間隔をあけて1段階ずつ行い,最大用量24mg(1回6mg 1日4回)まで。症状が強い場合や外来薬物治療ができない場合には,専門医の在籍する施設へ入院させる。
【副甲状腺癌】
初診時から著明な高カルシウム血症を呈している場合が多く,高カルシウム血症クリーゼのリスクが高い。
一手目 :生理食塩水2000~4000mL/日(点滴静注)
脱水の程度や飲水量・全身状態を勘案して投与量を決定する。
二手目 :〈一手目に追加〉ラシックスⓇ注(フロセミド)1回20~40mg(静注)患者の状態に応じて適宜増減
三手目 :〈一手目に追加〉エルシトニンⓇ注(エルカトニン)1回40単位1日2回(生理食塩水100mLに稀釈し1~2時間かけて点滴静注)
四手目 :〈三手目に追加〉ゾメタⓇ注(ゾレドロン酸水和物)1回4mg(生理食塩水100mLに稀釈し15分以上かけて点滴静注)
再投与は1週間以上あける。効果発現に2~3日を要するため,即効性のある生理食塩水補液やエルシトニンⓇ注の併用が原則である。
五手目 :〈三手目あるいは四手目に追加〉オルケディアⓇ2mg錠(エボカルセト)1回1錠1日2回(朝・夕,食前または食後)
増量は2週間以上の間隔をあけて1段階ずつ行い,最大用量24mg(1回6mg 1日4回)まで。
六手目 :〈三手目,四手目,あるいは五手目に追加〉デカドロンⓇ注(デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム)1回6.6mg 1日1~2回(生理食塩水100mLに稀釈し1時間かけて点滴静注)
カルシトニンのエスケープ現象の抑制,Caバランス陰性化,食欲増進作用を期待して投与する。骨吸収を促進するので短期投与にとどめる。
七手目 :〈骨転移を伴う場合,三手目あるいは四手目に追加,または処方変更〉ランマークⓇ注(デノスマブ)1回120mg 4週間に1回(皮下注)
デノタスⓇチュアブル配合錠などのCa補給薬は併用しない。
これらでもコントロールができない場合には,Caを含まない透析液を用いた血液透析を考慮する。
▶患者への説明のポイント
治療の第一選択は罹患副甲状腺摘出手術である。このため的確な診断が重要であり,高カルシウム血症が継続する場合は,必ず専門家受診を勧める。
日常生活においては,適切な食事・運動,および十分な飲水を指導する。天然型ビタミンDの不足は骨病変の増悪をもたらすため,食事からの摂取や日光への曝露を奨励する。また尿路結石症予防のため,水分摂取奨励,シュウ酸摂取制限に加えて,Caサプリメントと空腹時や食間のCa摂取を避けるが,食事からのCa摂取は奨励する。嘔気や多尿などの症状出現時には,急速に病状が悪化する場合があり,速やかに医療機関を受診するよう説明しておく。
【文献】
1)Yeh MW, et al:J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(3):1122-9.
2)Bilezikian JP, et al:J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(10): 3561-9.
中山耕之介(がん研有明病院糖尿病・代謝・内分泌内科部長)