お知らせ
心筋炎[私の治療]
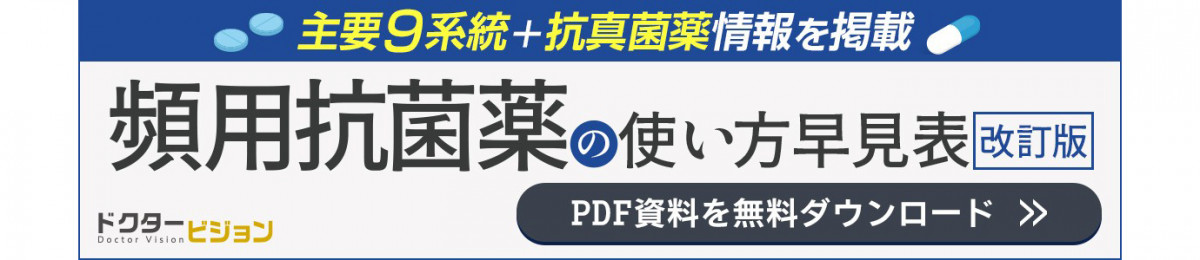
ウイルス,細菌などの微生物感染,薬物・毒物などへの曝露,免疫系の賦活化などを原因として,心筋組織への炎症細胞浸潤と心筋細胞傷害をきたし,心不全や致死性不整脈などを生じる。中でも感染症を契機とすることが多く,そのため感冒様症状や消化器症状が先行することが多いと言われている。軽症から重症まで幅広い臨床経過をとり,時には致死的となる疾患である。臨床病型は,急性,慢性活動性,慢性炎症性心筋症,心筋炎後心筋症に大別され,急性と慢性の境界線は発症から30日と定義されている1)。
▶診断のポイント
【症状】
心症状に先行して感冒様症状や消化器症状を呈する。息切れ,倦怠感,発熱等,非特異的な症状が多い。劇症型では低血圧やショックを呈する。
【検査所見】
血液検査では,心筋傷害を反映する高感度心筋トロポニンやCK-MBの上昇を認める。慢性活動性心筋炎では,1カ月以上遷延する心筋トロポニンの上昇を認める。ペア血清によるウイルス抗体価測定は原則推奨されない。心電図では,広範なST上昇,刺激伝導障害等を認める。劇症型では,しばしば高度房室ブロックや心室頻拍を伴う。心エコー図では,求心性心室壁肥厚,壁運動低下,心囊液貯留を認める。心臓MRIでは,炎症部位に一致した遅延造影像,T1値上昇に加え,T2高信号を認める。急性冠症候群との鑑別には,多くの場合,冠動脈造影が必要である。心内膜心筋生検は心筋炎の確定診断,治療方針の決定に重要であるが,サンプリングエラーによる偽陰性が存在する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
急性期における循環維持と進行性の心筋傷害を抑制することが治療の基本である。
循環動態が安定した患者では保存的に経過観察を行うが,循環破綻を伴い,しばしば致死的となる劇症型心筋炎では,早期診断と補助循環の機を逸しない導入が必要である。慢性期に心機能低下が遷延する症例に対しては,心保護薬の導入を行うなど一般的な心不全加療を行う。

残り1,626文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する











































