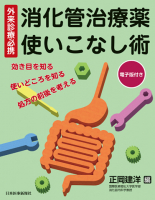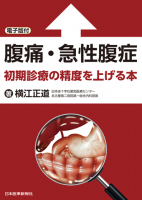お知らせ
過敏性腸症候群[私の治療]

器質的疾患を認めないにもかかわらず,消化管由来と考えられる症状を呈する疾患の総称が機能性消化管疾患であり,生命予後には影響しないものの,生活の質には影響する。その代表的疾患が過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)である。その診断基準は国際的な専門家からなるRome委員会によって定期的に見直されており,現時点で最新のものは2016年に発表されたRome IVである。Rome IVではIBSの診断基準は「週に1回以上の腹痛が診断の6カ月以上前に始まり,最近3カ月以内は持続する。なおかつ,①排便と関連する,②排便回数の頻度の変化を伴って症状が始まる,③便性状の変化を伴って症状が始まる,のうち2つ以上を満たす」とされている。2020年に日本消化器病学会から発表された「機能性消化管疾患診療ガイドライン2020―過敏性腸症候群(IBS) 改訂第2版」(以下,ガイドライン)においてもRome IV基準は有用であるとされている。
IBSは便性状,すなわち便秘便と下痢便の頻度の割合から便秘型,下痢型,混合型,分類不能型に亜分類される。上記を要約するとIBSは「便通異常と腹痛の双方を慢性的に呈する症候群」と言える。
▶診断のポイント
前述のごとく,IBSの主症状は腹痛,便通異常(下痢,便秘)である。IBSの特徴のひとつは慢性的な経過をたどることであり,上記の症状を呈しても症状の持続期間が週単位であれば,感染性腸炎等の急性の疾患を疑う。便通異常の原因として甲状腺疾患,糖尿病といった内分泌代謝疾患の可能性も考慮する必要がある。大腸内視鏡検査を受けたことがなければ,炎症性腸疾患や腸結核,近年,注目されている好酸球性胃腸炎の可能性も考慮する必要がある。特に好酸球性胃腸炎は粘膜面が正常でも顕微鏡的には好酸球浸潤を認めることがあり,生検による評価が必要である。精査の結果,Rome IV基準を満たせば,IBSと考える。


残り997文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する