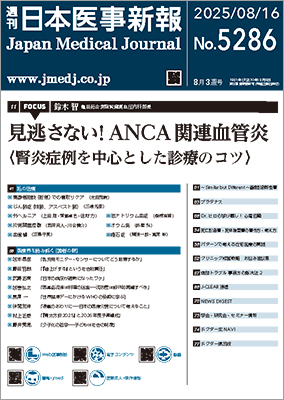お知らせ
喘息診断と呼気一酸化窒素濃度測定【軽症喘息でも容易に診断できる新しい診断ツール】

喘息は,「気道の慢性炎症を本態とし,臨床症状として変動性を持った気道狭窄(喘鳴,呼吸困難)や咳で特徴付けられる疾患」と定義される1)。喘鳴と寛解を繰り返すような典型症例では診断は容易であるが,軽症例,特に持続性の咳のみの場合(咳喘息とも呼ばれる)は診断に難渋する2)。こういった場合,これまでは喘息患者特有の気道炎症,すなわち気道への好酸球浸潤を喀痰などで確認し診断してきた。しかし,喀痰はすべての患者で採取は難しく処理に手間がかかることなどから,一般臨床では実施が困難であった。
あるいは,呼吸機能検査(スパイロメトリー)で閉塞性障害の変動性を1秒量の継時的変化や気管支拡張薬に対する可逆性(1秒量で200mLかつ12%の変化)で調べることも有用であるが,一般臨床ではあまり行われていない。

一酸化窒素(NO)は生体で産生されるガス分子である。喘息気道では,IL-4やIL-13といった好酸球性炎症に関わるサイトカインが,NO合成酵素も誘導し,NOの産生が高まる。つまり,気道の好酸球性炎症の程度と呼気NO濃度は正の相関関係を示す。呼気NO濃度と,アトピー素因や閉塞性障害などを組み合わせれば,軽症喘息でも容易に診断可能である。現在,2000以上の施設において呼気NO測定装置は使用されているので,診断に困ったら地域の呼吸器専門施設へ紹介頂きたい。
【文献】
1) 「喘息予防・管理ガイドライン2015」作成委員:喘息予防・管理ガイドライン2015. 協和企画, 2015.
2) 一ノ瀬正和:カラー版内科学. 門脇 孝, 他, 編. 西村書店, 2012, p774-6.
【解説】
一ノ瀬正和 東北大学呼吸器内科教授