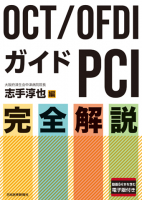お知らせ
高血圧症学[特集:臨床医学の展望2014]

各国における高血圧治療ガイドラインでの降圧目標見直しの潮流
2013年にはJNC 8,ESH/ESC 2013が発表された。2014年は我が国のJSH 2014が発表予定であり,いずれも「降圧目標値の見直しの潮流」の傾向にある。また,エビデンス重視の記載が目立つ。この中で降圧目標値は原則140/90mmHg未満である。一部の例外として,高齢者では原則150/90mmHg未満を目指す。また,糖尿病(diabetes mellitus;DM)の場合は我が国で130/80mmHg未満,ESH/ESCで140/85mmHg未満である。慢性腎臓病(chronic kidney disease;CKD)で蛋白尿(+)の場合は我が国で130/80mmHg未満,ESH/ESCで130/90mmHg未満である。
治療抵抗性高血圧は全患者の約10%に存在すると考えられている。その治療法の1つとして,中枢神経を介し,交感神経系を抑制する腎デナベーション法と頸動脈洞刺激術(baroreflex activation therapy;BAT)の臨床データが多数報告されている。その効果の報告は降圧のみならず,左室肥大退縮,non-dipperからdipperへの正常化,心不全の発症・進行抑制,インスリン抵抗性改善,睡眠時無呼吸症候群の抑制をはじめ枚挙にいとまがない。しかし,今後「最良の薬剤治療と比べて遜色がないのか,長期的血圧管理ならびに罹患率と致命的イベントの低減をもたらすのか」(ESH/ESC 2013)などの検討が必要となろう。
レニン・アンジオテンシン系(renin-angiotensin system;RAS)の研究も進んだ。臨床面では,RASの2剤併用療法の有効性を検討したいくつかの大規模臨床研究の結果は,低血圧,腎機能障害,高K血症などのデメリットが多く,有用性は認められず,各国ガイドラインでもACE阻害薬とARBの併用を推奨しないとした。基礎研究面では,RASの抑制が脂肪細胞機能改善,炎症反応抑制とともに糖・脂質代謝を改善することも明らかになりつつある。また,AT1(angiotensin Ⅱ type 1),AT2(angiotensin Ⅱ type 2)受容体の機能を調節する内因性蛋白ATRAP(AT1 receptor-associated protein)やATIP(AT2 receptor interacting protein)の機能も明らかとなり,AT2受容体刺激薬の開発も含め,新たな治療法の開発や病態生理学的役割の解明などが期待される。
ここ数年での,数十万人の遺伝子を用いたゲノムワイド関連解析(genome wide association study;GWAS)の結果,高血圧のなりやすさを規定する遺伝子数十個が明らかになった。一方,その血圧への影響は予想外に低いことも明らかとなった。高血圧の成因のうち約3割は遺伝因子が関与するとされており,GWASで明らかとなった多くの人の持つcommon variantに加え,rare variantの重要性が再認識されている。明らかとなった高血圧疾患感受性遺伝子を用い,本態性高血圧成立のメカニズムの解明や,そのオーダーメイド医療への応用が進められている。
近年,部位による血圧差(中心血圧),測定環境による血圧差(家庭血圧),測定時間帯による血圧差(夜間血圧),それらの血圧値の変動性などが予後予測因子として重要であることが確立しつつある。これらは現在,降圧治療上の最大の課題である高血圧患者の降圧目標値達成率(我が国の高血圧患者4300万人中,降圧目標達成者はその約1/4)を向上させる課題の次に来るであろう重要な課題である。「降圧の質(quality of blood pressure lowering;QOBPL)」の課題と言えよう。
最も注目されるTOPICとその臨床的意義
TOPIC 1/高血圧治療ガイドラインでの降圧目標見直しの潮流
2013年に発表されたESH/ESC高血圧治療ガイドライン2013,米国のJNC 8ともに降圧目標血圧値が緩和され,ほぼすべての疾患で140/90mmHg未満となった〔高齢者,糖尿病,蛋白尿(+)のCKDなどは異なる〕。2014年4月発表予定の日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン〔JSH 2014(案)〕も同様の方向である。
この1年間の主なTOPICS
1 高血圧治療ガイドラインでの降圧目標見直しの潮流
2 高血圧治療における交感神経系の役割の再評価 ─各種デバイスによる治療抵抗性高血圧治療
3 レニン・アンジオテンシン系に関する臨床・基礎面 での研究の進歩
4 大規模GWASによる高血圧関連遺伝子解明後の 機能解析と臨床応用を目指した動き
5 「降圧の質」重視の方向性─家庭血圧,夜間血圧,血圧変動,中心血圧

TOPIC 1▶高血圧治療ガイドラインでの降圧目標見直しの潮流
高血圧治療ガイドラインの改訂
近年,様々な高血圧治療ガイドラインが刊行されている。日本の高血圧治療ガイドラインは2009年版(JSH 2009)が改訂され,2014年4月にJSH 2014が発表される予定である。近年,英国NICEガイドライン1),KDIGO CKD高血圧ガイドライン20122),欧州高血圧学会(ESH)を中心としたESH/ESC 20133)などが発表され,米国においてはJNC 7(2003年)以来,10年ぶりにJNC 84)が発表された。
ESH/ESC 2013,JNC 8における血圧分類と降圧目標
ESH/ESC 2013において,3つ以上のリスク因子を有する症例と,メタボリックシンドローム・subclinicalな臓器障害・糖尿病(DM)などが同じリスク分類に含まれていたが,新基準では,subclinicalな臓器障害・CKD stage 3以上・DMは,リスクを1ランク上げて,よりリスクが高いグループとして記載されている。結果として,リスクの異なるグループが5段階となっており,かなり複雑なリスク評価表となっている。
降圧目標は,ESH/ESC 2007では低〜中等リスク群で140/90mmHg未満,DM・脳血管疾患・心血管疾患・CKDを含む高リスク群で130/80 mmHg未満であった。ESH/ESC 2013では降圧目標がより緩和され,JNC 8とともに降圧目標はほぼすべての疾患で140/90mmHg未満とした。DM患者の降圧目標はFEVER試験,HOPE研究,ADVANCE試験などを引用し,ESH/ESC 2013では140/85mmHg未満としている。
一方,ESH/ESC 2013では80歳未満の高齢高血圧患者の目標収縮期血圧(systolic blood pressure;SBP)を140〜150mmHgとしているが,健康状態が良好な80歳未満であれば140mmHg未満としてもよいと記載されている。しかし,全身状態などを個別に検討する必要があるとされている。さらに80歳以上の高齢者に関してはSBPが160mmHg以上で,肉体的にも精神的にも良好な患者には,SBP 140〜150mmHgを目指した治療を推奨している。JNC 8では60歳以上で150/90 mmHg未満とし,降圧薬治療でSBP 140mmHg未満で忍容性が良ければそのままでよいとしている。なお,ESH/ESC 2013では,拡張期血圧(diastolic blood pressure;DBP)に関しては,どのような病態でも90mmHg未満が推奨されている。唯一の例外はDM患者であり,FEVER試験,HOT研究,UKPDS38などを引用して,降圧目標をDBP 85mmHg未満としている。なお,DBP 80〜85mmHgについてもDM患者では安全で忍容性があるとの記載があり,例外的な対応となっている。
CKDと降圧目標
蛋白尿の少ないCKDに対する降圧効果の検討(AASK研究)や,DM患者への厳格降圧の非有用性(ACCORD研究)などを反映し,KDIGO CKD高血圧ガイドライン2012(保存期CKDへの降圧指針)では,DMの有無にかかわらずアルブミン尿が30mg/日未満のCKDでは,血圧が140/90 mmHgを超えたら140/90mmHg以下を降圧目標として降圧するとされた。一方,アルブミン尿が30mg/日以上である場合は,130/80mmHgを超える血圧を示す場合に130/80mmg以下を目標とすることとした。
最新のCKD診療ガイドライン2013では,非DM合併CKDに対しては降圧目標を140/90mmHg未満に維持することとし,蛋白尿0.15g/gCr(アルブミン尿30mg/gCr)以上の患者では,130/80mmHg未満を目指すとした。一方,DM合併CKDの降圧目標は,蛋白尿やアルブミン尿がない症例でも130/80mmHg未満を推奨するとしており,KDIGOとの違いがある。ACCORD研究やメタ解析でSBPを130mmHg未満にすることで脳卒中抑制効果が示されており,脳卒中の多い日本人の特異性を鑑みた推奨となっている。
ESH/ESC 2013では,CKDは他の疾患と同様にSBP 140mmHg未満,顕性蛋白尿があれば130mmHg未満を降圧目標とした。DBPも他疾患と同じ90mmHg未満であるが,DM(腎症)では85mmHg未満を推奨している。
ABPMを用いた血圧評価の現状
2011年のNICEガイドラインでは,診察室血圧が140/90mmHgを超えている場合は,24時間自由行動下血圧測定(ambulatory blood pressure monitoring;ABPM)を用いて高血圧を確定診断するように記載された(ただし,ABPMに耐えられない人は家庭血圧を用いてもよい)。一方,ESH/ESC 2013では,ABPMは家庭血圧測定とともに診察室外(out-of-office)血圧として定義されており,心血管リスクをよりよく予測すると評価しているが,全例に施行することを義務づけるような記載は認めていない。今後は,AB PMや家庭血圧をターゲットとしたエビデンスレベルの高い臨床研究がなされ,ABPMによる血圧値評価の立ち位置が明らかにされるとともに,疾患ごとのABPM値を用いた降圧目標値の設定が,高血圧ガイドラインにも記載されてくるものと思われる。
(平和伸仁,戸谷義幸,安田 元)
◉文 献
1) Hypertension Clinical guideline 127:clinical management of primary hypertension in adults(update).2011.
[http://guidance.nice.org.uk/CG127]
2) Group., K.D.I.G.O.K.B.P.W.:Kidney Int. 2012;2(Suppl.):337-414.
3) Mancia G, et al:J Hypertens. 2013;31(7): 1281-357.
4) James PA, et al:JAMA. 2013 Dec 18;doi: 10.1001/jama.2013.284427. [Epub ahead of print]
TOPIC 2▶高血圧治療における交感神経系の役割の再評価 ─各種デバイスによる治療抵抗性高血圧治療
最近,高血圧の発症と病態の維持に交感神経活動の亢進が関与していることが注目され,交感神経を抑制する新しいデバイス治療が発明された。腎交感神経アブレーションとBATは,主に治療抵抗性高血圧を対象とする臨床試験において,長期間にわたって持続的な降圧効果を示すことが明らかにされた。これらは侵襲的な手技でもあるため,手技に伴う合併症のさらなる抑制が今後とも必要とされるが,長期的な降圧効果以外に交感神経活性抑制による臓器保護効果も期待されており,高血圧以外の病態への適応に向けてさらなるエビデンスの蓄積が期待される。両治療法は,手技は異なるものの最終的には交感神経活動を抑制する効果があり,長期間の治療戦略が必要となる高血圧においても,画期的な治療として普及が期待される。
高血圧において体液性因子以外の因子として動脈圧受容器反射を含む自律神経による調節が重要であることは周知の事実であり,古くから多くの自律神経による循環調節に対する研究が行われてきたが,自律神経による血圧調節の効果は比較的短期間に限られており,慢性的な病態における役割は限定的と考えられていた。しかし,近年の研究成果により,動脈圧受容器反射を含めた自律神経系の関与は強力な長期効果もあることが明らかとなり,交感神経活動を抑制する治療法が脚光を浴びるようになってきた。
腎交感神経アブレーションは,主に腎動脈の外膜に分布する腎周囲交感神経を,大腿動脈から経皮的に挿入したカテーテルを用いて腎動脈の内側から低出力高周波エネルギーで交感神経のみを焼灼する治療法である。腎交感神経アブレーションは,主に治療抵抗性高血圧患者を対象に臨床試験が行われ,36カ月後も優れた長期にわたる降圧効果を得ている1)。治療抵抗性高血圧の降圧作用以外にも,交感神経の異常によって起こる様々な病態を改善させる作用および病態の適応が期待されている。一方,降圧薬治療に比べ降圧の程度は診察室ではよく下げるが,ABPMでの血圧低下は少ないとする報告もある2)。
一方, BATは動脈圧受容器反射を利用した治療法である。2004年に米国CVRx社が開発した頸動脈洞刺激デバイス(Rheos®SystemTM,CVRx Inc.)が販売承認を受け,これも22〜53カ月といった長期間のフォローアップでも有意な降圧を達成していることが示されている3)。近年,ジェネレーターを小型化し,頸動脈洞リードを2本から1本に簡素化した第2世代のデバイス(Barostim neoTM)も登場し,この第2世代デバイスを用いた試験では,腎動脈アブレーション無効例に対しても効果を認めた症例も報告されている4)。将来的に,デバイスの機能を拡張して血圧をリアルタイムにセンシングすることができれば,その情報を基に電気刺激頻度を調節し,血圧変動を制御できることから,より質の高い降圧治療を達成できる可能性がある。さらに,交感神経活動の抑制により心不全に対しても圧受容器刺激が有効であることはヒトでも報告されてきており5),慢性心不全患者などへの適応拡大も期待されている。
(中森 悠,橋本達夫,菅野晃靖)
◉文 献
1)Krum H, et al:Lancet. 2013;pii:S0140-6736(13)62192-3.
2)Parati G, et al:Circulation. 2013;128(4) :315-7.
3)Bakris GL, et al:J Am Soc Hypertens. 2012; 6(2):152-8.
4)Hoppe UC, et al:J Am Soc Hypertens. 2012;6(4):270-6.
5)Doumas M, et al:Curr Hypertens Rep. 2012; 14(3):238-46.
TOPIC 3▶レニン・アンジオテンシン系に関する臨床・基礎面での研究の進歩
RAS阻害薬の併用投与が心・腎臓器障害の抑制に及ぼす影響について,多くの注目すべき知見が示された。ALTITUDE試験では,すでにアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬またはアンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)による標準治療を受けている心・腎イベント高リスク2型DM患者を対象とし,心・腎イベント抑制についてレニン阻害薬アリスキレンまたはプラセボの併用を比較し,アリスキレン併用群で蘇生を要する心停止,低血圧,高K血症を多く認めた。また同群では尿中アルブミン・クレアチニン比の低下を認めたものの,腎アウトカムを改善しなかった。試験登録患者の8割以上にRAS阻害薬がすでに投与されていたASTRONAUT試験1)では, 左室収縮能の低下した慢性心不全入院患者においてアリスキレン追加投与による有用性は認められず,低血圧および腎機能障害が有意に多かった。
一方ACE阻害薬とARBの併用療法でも,顕性アルブミン尿を有する2型DM合併慢性腎不全患者を対象としたVA NEPHRON-D試験2)では,併用投与群でARB単剤投与群と比較して急性腎不全および高K血症が有意に多かったため,早期中止された。この結果は,ONTARGET試験のサブ解析などと同様の結果であった。
以上の知見からは,過度なRAS抑制により結果としてアルブミン尿を減少しえたとしても心・腎アウトカムを改善せず,低血圧や腎機能障害,高K血症といった副作用が高頻度に引き起こされたものと総括される。これらを受けてESH/ESC 2013ではACE阻害薬とARBの併用を推奨しないとした。
基礎研究では,脂肪組織におけるRASの病態生理学的意義が注目されている。脂肪組織にはアンジオテンシノーゲン(angiotensinogen;AGT),レニン,AT1受容体などのRAS構成要素がすべて発現している。例えばげっ歯類の循環血漿中AGTのうち約30%は脂肪細胞から産生されている。脂肪組織における炎症はインスリン抵抗性,メタボリックシンドローム形成に重要であるが,RASが脂肪細胞の分化や炎症反応の制御に関与することが報告されている。例えば脂肪組織に特異的にAGTを欠損させたマウスでは,高脂肪食負荷による肥満高血圧が抑制されたとの報告もなされた。また,Ang Ⅱ/AT1受容体系に拮抗する系として,AT2受容体系に加えてACE2-Ang(1-7)/Mas受容体系があるが,脂肪細胞・組織においてもAng Ⅱ/AT1受容体系とACE2-Ang(1-7)/Mas受容体系のバランスが脂肪細胞・組織機能制御に関与することや3),Ang(1-7)投与がメタボリックシンドロームモデルラットの脂肪細胞機能改善,炎症反応抑制とともに糖・脂質代謝を改善することが報告されている。
一方最近では,Ang Ⅱ受容体に特異的に結合し,その機能を調節するAng Ⅱ受容体結合蛋白の糖・脂肪代謝制御における作用に関する研究結果も複数報告されている。AT1受容体に結合する蛋白のATRAPはAT1受容体C末端に特異的に結合し,持続的に同受容体の細胞内への取り込み(internalization)を促進することで, 生理的なAT1受容体情報伝達系には影響を与えずに,病的刺激によるAT1受容体系の過剰活性化を選択的に抑制する可能性が指摘されている4)。全身性ATRAP欠損マウスは,生理的条件下では血圧の変化や腎の形態・発生異常は認められていないが,病的刺激として高脂肪食を投与すると,野生型マウスと比較して脂肪細胞の大型化を伴った内臓脂肪組織重量の増加が見られ,脂肪組織への炎症性マクロファージ浸潤の亢進が認められるとともに,糖・脂質代謝指標の悪化が見られた。興味深いことに,ATRAPを高発現させたマウスの脂肪組織をATRAP欠損マウスの皮下に移植すると,ATRAP欠損マウスの糖代謝異常の有意な改善が認められた。
一方,AT2受容体に関しては最近非ペプチド性のAT2受容体刺激薬が開発され,臓器保護作用が報告されるとともに臨床応用が期待されているが,AT2受容体に結合してその機能調節を行うATIPの存在も報告されている。全身性ATIP1過剰発現マウスに高脂肪食を負荷した場合に,野生型マウスに比較して脂肪細胞の大型化が抑制されるとともに,脂肪組織での炎症性サイトカイン発現および炎症性マクロファージM1の脂肪組織内浸潤が有意に抑制されることが報告された。以上の研究結果は,脂肪組織RASと糖・脂肪代謝制御および,その異常との関連性を支持するものであり,RASの制御がDM,メタボリックシンドロームの治療ターゲットとなる可能性が示唆される。
(大澤正人, 畝田一司, 田村功一)
◉文 献
1)Gheorghiade M, et al:JAMA. 2013;309 (11):1125-35.
2)Fried LF, et al:N Engl J Med. 2013;369 (20):1892-903.
3)Than A, et al:J Biol Chem. 2013;288 (22):15520-31.
4)Wakui H, et al:Hypertension. 2013; 61(6):1203-10.
TOPIC 4▶大規模GWASによる高血圧関連遺伝子解明後の機能解析と臨床応用を目指した動き
大規模GWASと機能解析
2000年以降,ヒトゲノム配列の解析がなされたことで新しい病因解明・治療・予防への貢献が期待され,様々な疾患で新たな知見が得られた。しかし高血圧症に対する結果は,Wellcome Trust Case Control Consortium(WTCCC)による報告をはじめ,初期のゲノムワイド関連解析(GWAS)はまだまだ挑戦的かつ再現性の乏しい解析結果であった。
2009年,Nature Genetics誌に報告された第2報が第二期GWASの幕開けである。Global BPgen(Global Blood Pressure Genetics)と,英国を中心とするCHARGE(Cohorts for Heart and Aging Research in Genome Epidemiology)からその成果が報告された。ATP2B1遺伝子は,GWASによって浮かび上がった,高血圧症に関与しうるとされた有力な候補遺伝子の1つである。
その後も様々な人種でATP2B1を含むこれらの遺伝子のSNPsが高血圧症に感受性のある遺伝子であると再現されている。さらに,血圧とは独立して冠動脈疾患や冠動脈石灰化1),心不全などのリスクとなることが報告されている。その機能や血圧に影響を与えるメカニズムに注目が集まったが,in vivoでATP2B1と高血圧との関連を報告した論文は小林らの報告2)のみである。
臨床的意義
種々のメタ解析で同定されているcommon variantは集団に対する血圧値の影響はわずか1mmHg前後である。これは血圧の約3%を説明するにすぎず,これらの知見が患者の治療において利益になるのだろうか? これを解決するのが,rare variantや測定方法の均一化などのアプローチかもしれない。2013年に発表された注目の論文は,1つ目がrare variantと関連しており,2つ目が薬理遺伝学からのアプローチである。
①体細胞変異が血圧に影響
1つ目は,Beuschleinら3)が報告したATP1A1とATP2B3の体細胞変異はアルドステロン産生腫瘍と二次性高血圧を引き起こすというものである。アルドステロン産生腺腫に対しエクソームの塩基配列決定を行った。そして,ATPaseファミリーであるATP1A1とATP2B3の変異を副腎細胞の7%に同定した。稀な変異であるが,細胞内Ca濃度を増加させアルドステロン産生増加を介して血圧上昇につながると考えられた。これらのファミリーにATP2B1があり,こちらはcommon variantに関連する変異であり,その意義の解明が期待される。
②HOMED–BP研究
2つ目は,HOMED-BP研究4)である。同研究は世界で初めて降圧薬の反応性を調べたGWASである。265人の患者をCa拮抗薬(CCB),ACE阻害薬,ARBに割り付けて解析した。CCBには6つのSNPsを,ARBには2つのSNPsを同定している。降圧薬治療のテーラーメイド医療の第一歩となる報告であるとともに,家庭血圧をきわめて正確に測定していることが他の研究と一線を画している。従来の診察時血圧に比較して測定の精密さやばらつきが小さく,血圧値の意味が高いことが,265人という決して多くはない人数で一定の成果を挙げた要因と考えられる。ほかに,サイアザイド系利尿薬への反応性に関与するprotein kinase C α(PRKCA)やG蛋白α subunit(GNAS)も報告された5)。
(谷津圭介,平和伸仁)
◉文 献
1) Ferguson JF, et al:J Am Coll Cardiol. 2013; 62(9):789-98.
2) Kobayashi Y, et al:Hypertension. 2012; 59(4):854-60.
3) Beuschlein F, et al:Nat Genet. 2013;45 (4):440-4, 444e1-2.
4) Kamide K, et al:Pharmacogenomics. 2013; 14(14):1709-21.
5) Turner ST, et al:Hypertension. 2013;62 (2):391-7.
TOPIC 5▶「降圧の質」重視の方向性 ─家庭血圧,夜間血圧,血圧変動,中心血圧
「降圧の質(QOBPL)」を考慮した適切な降圧療法とは,診察室血圧のみならず,家庭血圧やAB PMといった診察室外血圧値,血圧変動(blood pressure variability;BPV),夜間血圧,さらに中心血圧などの改善をもたらす療法である。本稿では,夜間血圧およびBPVを中心に最近の知見を述べる。
夜間血圧
近年,夜間血圧の臨床的意義がABPMにより実証され,昼間の血圧よりも心血管予後を反映し,心血管リスク増加に関与するとのコンセンサスが得られている。大迫研究によると,ABPMにて夜間の血圧降下度が5%減少すると,心血管死のリスクが20%増加することが報告されている。
夜間血圧は左心室肥大の進展・発生に相関を認め,心房細動患者においては,左心房径および心房性ナトリウム利尿ペプチドとの相関が認められた。加齢で増加し,夜間血圧降下度は40歳以前では変化はないが40歳以後から2.8%/1歳で低下しており,60歳以上では60歳未満と比較してriser typeの割合が4倍であった。non-dipper typeやriser typeのリスクは,夜間高血圧によってもたらされると考えられるが,24時間にわたる正常血圧者においても,non-dipper typeやriser typeの心血管系イベントのリスクは高い1)。夜間血圧は推算GFRの低下とともに上昇し,蛋白尿の程度とも相関し,non-dipper typeやriser typeの高血圧はCKD進行およびCVD合併のリスクとなることが明らかにされている2)。
近年,ABPMによる血圧日内変動評価を含めた高血圧診断のガイドラインも提唱された3)。しかし,夜間高血圧のみを治療目標とした高血圧治療の有用性は明らかでなく,今後の検証が必要である。また夜間血圧の測定,血圧日内変動性の判定には主にABPMが用いられてきたが,最近では睡眠時血圧を測定できる家庭血圧計も実用可能であり,家庭夜間血圧はABPMと大差なく,臓器障害の関連も同程度であったとも報告されている。ABPMは必ずしも再現性が高くなく,また患者の身体的負担も大きいため,今後は家庭血圧計の併用による夜間血圧の管理も期待される。
血圧変動
一口にBPVと言っても様々であり, 超短期BPV(診察時のBPV,within-visit variability;WVV)から短期BPV(ABPMによるBPV, short-term variability;STV),長期 BPV(診察ごとのBPV,visit-to-visit BP variability;VVV)などに分かれる。これらのBPVは一様に脳・腎・心血管系イベントの危険因子として確立しつつある。
2010年にRothwellらによってVVVが脳卒中および心疾患の重大な危険因子になることが初めて報告されて以来,同概念に対する研究はより詳細に行われている。VVVは脳卒中の既往のある患者において微小脳出血の,心血管疾患高リスクである高齢者において認知機能障害の危険因子になると報告されている4)。保存期CKD患者においてeGFR低下,全死亡率の危険因子になることや,維持透析患者においても心血管死の危険因子になることが報告されている。また,アルテプラーゼ(rt-PA)静注療法を受けた脳梗塞患者において,治療後25時間のBPVが症候性脳出血と死亡率の危険因子になると報告された。
本態性高血圧症患者においては睡眠時無呼吸症候群が夜間BPVを増加させ,無治療の本態性高血圧症患者においては24時間BPVが血圧値に関係なく多臓器障害の独立した危険因子である。昼間BPVは腎機能障害,夜間BPVは動脈硬化症の危険因子である。また,筆者らはCKD患者においてBPVの改善を伴う降圧治療によりアルブミン尿や心肥大の改善効果が増強することを明らかにしている。近年BPVはより詳細に研究されるようになってきており,個々の病態におけるBPVの臨床的意義の評価やその機序の究明にまで及ぶようになっている。一方で,疾患バイアスのない一般集団ではVVVやSTVは血圧値ほどの心血管イベント予測因子にならないとする報告も最近出てきており,今後もさらなる研究,検討が必要と考えられる。
(小林 竜,小豆島健護, 田村功一)
◉文 献
1) Hermida RC, et al:Chronobiol Int. 2013;30 (1-2):87-98.
2) Hermida RC, et al:Nat Rev Nephrol. 2013; 9(6):358-68.
3) O'Brien E, et al:J Hypertens. 2013;31 (9):1731-68.
4) Sabayan B, et al:BMJ. 2013;347:f4600.