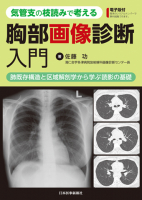お知らせ
【他科への手紙】呼吸器内科→病理部

呼吸器疾患の診断は、臨床的所見、画像所見、病理所見を総合して行っており、病理の先生には肺癌の診断だけではなく、びまん性肺疾患などの良性疾患の診断についても大変お世話になっております。今回は、その中でも近年、病理の先生に形態学的診断だけでなく免疫染色や遺伝子学的検索等でいろいろとお願いすることが増えている、非小細胞肺癌の話題について述べさせて頂きます。
現在はニボルマブとペムブロリズマブという免疫チェックポイント阻害薬が、非小細胞肺癌の化学療法で使用されるようになりました。従来とは異なる作用機序と効果を持ち、化学療法の主要な選択肢の1つとなっています。

組織検体の免疫染色によるPD-L1検査でのPD- L1の発現率(TPS)は治療効果の予測につながります。TPS 50%以上の場合にはペムブロリズマブが化学療法の一次治療薬として使用できるため、治療薬選択の判断材料とさせてもらっています。当院では組織診断時にPD-L1の免疫染色も院内で測定して頂けており、治療薬の選択の際に迅速な判断を行うことができ大変助かっています。
がん細胞の発生・増殖・生存にきわめて重要な遺伝子変異とその遺伝子異常を標的とする分子標的治療薬として、ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブといった、EGFR(上皮増殖因子受容体)遺伝子変異に対するチロシンキナーゼ阻害薬(以下 EGFR-TKI)があります。診断時にEGFR遺伝子変異の検索のために病理の先生に検体を作成して頂き検査しています。

残り520文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する