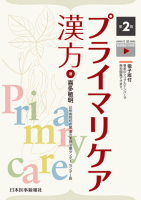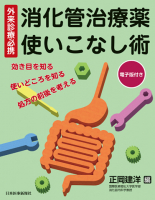お知らせ
実臨床における便秘の漢方治療について
便秘薬は漢方薬のみならず,西洋薬でも多種多様であり,使い分けが難しい場合があります。そこで,実臨床における便秘の漢方治療についてご教示下さい。山口総合健診センター・飯塚徳男先生にご解説をお願いします。
【質問者】中永士師明 秋田大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学講座教授

【回答】
【慢性かつ機能性便秘の患者に対して,体質に沿った漢方薬を選ぶ】
便秘はその成因から器質性・薬剤性・症候性・機能性の4つのタイプに,また,発症や経過から急性・慢性の2つのタイプに分類されます。本稿では,安心して漢方介入ができ,その臨床効果が期待できる,慢性かつ機能性便秘に用いる漢方薬に焦点を当てて解説します1)。
慢性・機能性便秘の中で弛緩性便秘を呈する患者の多くは,漢方的に実証タイプ(病原に対する反応性が高く,暑がりタイプ)と考えられるため,腸蠕動を高める大黄(主成分はアントラキノン誘導体であるセンノシド)を含有する漢方薬(大黄甘草湯・桃核承気湯・防風通聖散)を用途に応じ使い分けます2)。痙攣性便秘を呈する患者の多くは,漢方的に虚証タイプ(病原に対する反応性が乏しく,冷え症で元気のないタイプ)と考えられるため,第一選択薬としてマイルドに作用する桂枝加芍薬湯や小建中湯を用い,効果が乏しければ,桂枝加芍薬湯に大黄を少量加えた桂枝加芍薬大黄湯を用います2)。これらの芍薬がベースとなった漢方薬が奏効する患者では腹皮拘急(腹直筋の攣縮)が認められます。

残り615文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する