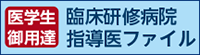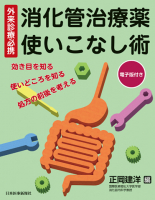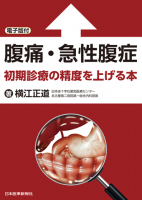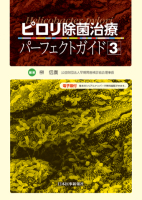お知らせ
過敏性腸症候群[私の治療]
薬物療法は,優勢症状に合わせた薬剤選択を行う。病型にかかわらず有効であるプロバイオティクス,消化管運動機能調整薬であるトリメブチンマレイン酸塩,消化管内で水分を保持して消化管内容物の輸送調節作用があるポリカルボフィルカルシウムを用いる。さらに,下痢型の場合には,止痢薬(ロペラミド)や5-HT3拮抗薬(ラモセトロン塩酸塩)を用いる。便秘型では,緩下剤(酸化マグネシウムなど)や粘膜上皮機能変容薬で硬便の改善を図る。高齢者や腎機能低下例では,酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症に注意が必要である。刺激性下剤は腹痛を増悪させる可能性もあり,連用を避け,使用する場合でも頓服で用いる。腹痛優位の症例では,禁忌を確認の上,抗コリン薬を併用する。これらの治療を4~8週継続し,改善しない場合には第2段階へ移行する。
第2段階では,IBSの病態生理のひとつであるストレスや心理的異常の評価を行う。腹痛優位の症例や抑うつを伴う症例では,抗うつ薬の追加を考慮する。うつ症状がない症例でも,下行性疼痛抑制系の賦活作用で腹痛改善効果がある。不安が強い症例で抗不安薬の投与も考慮するが,依存に注意が必要である。これらの治療でも効果不十分,無効の場合には第3段階へ移行するが,第3段階では中等症~重症例を対象としており,専門施設での診療が中心となる。

▶治療の実際
一手目 :〈病型にかかわらず〉セレキノンⓇ100mg錠(トリメブチンマレイン酸塩)1回1~2錠1日3回(毎食後),またはポリフルⓇ500mg錠(ポリカルボフィルカルシウム)もしくはコロネルⓇ500mg錠(ポリカルボフィルカルシウム)1回1~2錠1日3回(毎食後),またはミヤBMⓇ20mg錠(酪酸菌)1回1錠1日3回(毎食後)もしくはラックビーⓇ10mg錠(ビフィズス菌)1回1~2錠1日3回(毎食後)
二手目 :〈便秘型,一手目に追加〉酸化マグネシウム250mg錠・330mg錠(酸化マグネシウム)1回1~2錠1日3回(毎食後),またはリンゼスⓇ0.25mg錠(リナクロチド)1回1~2錠1日1回(朝食または昼食前)1回1錠から開始し,効果不十分の場合は増量を考慮,またはアミティーザⓇ12μgカプセル・24μgカプセル(ルビプロストン)1回1カプセル1日1~2回(朝・夕食後)
いずれも便性状に応じて用量調整する。
二手目 :〈下痢型,一手目に追加〉イリボーⓇ2.5μg錠・5 μg錠(ラモセトロン塩酸塩)1回1錠1日1回(朝食後)
女性では2.5μgから開始し適宜増量する。下痢症状が強い場合,ロペミンⓇ1mgカプセル(ロペラミド塩酸塩)1回1カプセル1日1回(朝食後)。いずれも便性状に応じて用量調製,または休薬する。
【参考資料】
▶ 日本消化器病学会, 他:機能性消化管疾患診療ガイドライン2020—過敏性腸症候群(IBS).改訂第2版. 南江堂, 2020.
福田眞作(弘前大学学長)