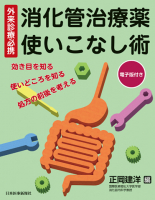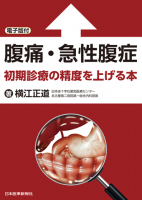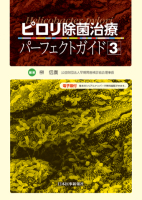お知らせ
腸管ベーチェット病/単純性潰瘍[私の治療]
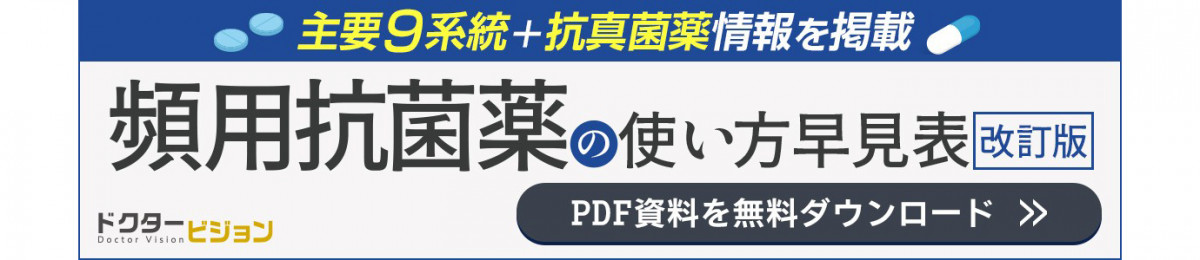
ベーチェット病(Behçet’s disease:BD)は,①再発性口腔内アフタ,②皮膚症状,③眼症状,④外陰部潰瘍を主徴候とする難治性全身性炎症性疾患である。指定難病であり,特定疾患医療受給者数からみた患者数は1万9147人(2013年3月末時点)である1)。BDの3~16%に消化管病変が合併する。腸管BDの定型的な回盲部の潰瘍病変はフラスコ型と称されるUl-Ⅳの深い潰瘍で,穿孔や穿通のリスクを伴う。
▶診断のポイント
腸管BDはBDの一病型として位置づけられ,神経型,血管型とともに特殊型に分類される。厚生労働省ベーチェット病に関する調査研究班の診断基準に基づいて,完全型あるいは不全型BDの基準を満たし,かつ回盲部の定型病変を認める場合に腸管BDと診断される。各症状は同時に出現する必要はなく,病歴の中で出現したことがあればカウントされる。
単純性潰瘍は「回盲部近傍の慢性打ち抜き様の潰瘍」「境界明瞭な円形ないし卵円形で下掘れ傾向が強く,回盲弁上ないしその近傍に好発し,組織学的には慢性活動性の非特異性炎症所見を示すUl-Ⅳの潰瘍」と定義される。
腸管BDと単純性潰瘍を内視鏡所見あるいは病理所見で鑑別するのは困難であり,両者の鑑別は腸管外症状の有無でなされる。単純性潰瘍と診断されたのち腸管外症状が出現し,腸管BDの診断がつくことはありうる。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
腹部症状が無症状あるいは軽症で内視鏡所見も軽度の症例に対する薬物治療のエビデンスは少ないが,5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤やサラゾスルファピリジンの有効性が報告されている。もし無投薬で経過観察する場合は,定期的にCRPなどの炎症マーカーでフォローし,腸管外症状の出現にも注意する。
中等症以上の自覚症状を伴い,内視鏡的にも典型的な深掘れ潰瘍が存在する場合は,副腎皮質ステロイドまたはTNF阻害薬(アダリムマブ,インフリキシマブ)の適応である。副腎皮質ステロイドは多くの使用経験に基づいた実績があり,中等症以上の寛解導入治療としては今もって第一選択となりうる。一方,維持投与による再燃予防のエビデンスはなく,副作用の観点から副腎皮質ステロイドの長期使用は可能な限り避けるべきである。TNF阻害薬は日本国内で臨床試験が行われ,有効性が確認されている。速やかな臨床症状の改善に加え,継続投与による寛解維持効果,さらに内視鏡所見の改善も期待できる。

残り1,706文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する