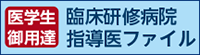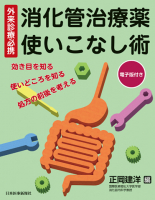お知らせ
低侵襲手術でも「取扱い規約」分類をすべき?【内視鏡的粘膜切除術などでは不要】
【Q】
胃癌や大腸癌の「取扱い規約」に書いてあるGroup分類は,内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection:EMR)などの小手術の検体の場合でも,参考のため「Group 3相当」などと記載するものですか。 (兵庫県 K)

【A】
『胃癌取扱い規約(第14版)』,『大腸癌取扱い規約(第8版)』ともに,生検組織診断分類(Group分類)の項目において,内視鏡的生検材料を対象とし,ポリペクトミー材料,内視鏡的粘膜切除材料,内視鏡的粘膜下層剥離材料や外科切除材料は除外すると記載してあります。そのため,ご質問のようにEMR検体に対し,「Group 3相当」と記載することは一般的ではありません。一方,Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia(文献1)では,生検のみならず,切除材料にも用いられるとされています。
Group分類は,胃と大腸の上皮性のものにのみ用いられ,非上皮性病変や食道生検などでは使用しません。Group分類では胃・大腸ともにGroup X,1,2,3,4,5のいずれかを記載しますが,Group 2には腫瘍性(腺腫またはがん)か非腫瘍性か,判断が困難な病変が含まれるので,注意が必要です。特に,胃の旧Group分類では,腫瘍か否か判定が困難な病変に対しては,腺腫とともにGroupⅢが適応されていましたが,『胃癌取扱い規約(第14版)』では,Group 2が適応されることになっています。そのため,Group 2の範疇とした場合は,判定困難な理由とともに疑われる診断名を必ず記載し,再生検による診断確定を行わなくてはなりません。
また,生検は,あくまで病変の一部の採取であることにも留意する必要があります。生検と内視鏡切除標本での病理診断に乖離を認めた症例を解析した報告もあるため(文献2),再生検や内視鏡的特徴などを含め,総合的に診断することが重要です。
【文献】
1) Schlemper RJ, et al:Gut. 2000;47(2):251-5.
2) Takao M, et al:Gastric Cancer. 2012;15(1):91-6.