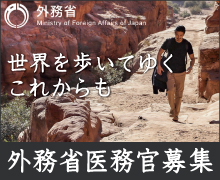お知らせ
薬師寺泰匡
- 登録日:
- 2022-01-13
- 最終更新日:
- 2025-08-18
「破傷風ワクチン供給停止の今、外来診療で注意すべきこと」
2025年7月、『沈降破傷風トキソイド』が入手できなくなるという衝撃的な状況となっている。沈降破傷風トキソイド「生研」について、製造販売元であるデンカ株式会社からの入庫遅延が発生し、2025年6月19日から限定出荷になるということであった。当初はなんとかなる見込みだったものが、製造工程の問題から、2025年7月9日に製品出荷を停止するという報告がなされた。デブリードマンを要するような外傷では、破傷風対策は必須である。沈降破傷風トキソイドがない場合、ヒト破傷風免疫グロブリンを投与するしかないが、需要が高まったため、こちらも出荷調整がかかるという状況にまで至った。全国の救急現場には緊張が走っている。これは単なる一時的な供給遅延ではない。破傷風という忘れられがちな感染症への備えが、今まさに脆弱化しているのである。
破傷風は、Clostridium tetaniが産生する神経毒素によって発症する疾患であり、治療が遅れれば致死率は高い。外傷歴がはっきりしない高齢者に発症する例もあり、「農作業中に手を切った」「庭で転倒し擦り傷を負った」など、救急外来ではめずらしいものではない。筆者の経験では、汚染創に気づかず、数日後に開口障害と項部硬直で搬送された中年男性が、ICUでの長期治療を要した。トキソイド未接種が背景にある。このような状況下で、地域の外来診療を担う先生方にお願いしたいのは以下の2点である。
第一に、受傷初期におけるワクチン接種歴の確認である。
問診時には、「小児期の3種混合ワクチン(DPT)は受けたか」「成人後にトキソイドの追加接種をしたか」を意識的に確認頂きたい。破傷風ワクチンは、1968年10月15日に定期接種が開始され、その後、副作用の問題で1975〜81年の間にはDPTワクチンの接種が一時的に中止された。この未接種時期に当てはまる方には、特に注意が必要である。未接種でハイリスクな創の場合、破傷風予防は必須である。
第二に、破傷風トキソイド以外の予防策を十分とることである。
トキソイドは発症予防のワクチンであり、既に神経症状が出ている患者には無効である。すなわち、発症後の治療には免疫グロブリンの早期投与と集中治療が必要であるが、その備えが脆弱化している今、「予防」がいっそう重要になる。現場では、創傷処置後にワクチンを打つべきか否か、免疫グロブリンを求めて近隣の病院を探すか否か、きわめて悩ましい判断が続いている。だからこそ、「初期対応」が患者の予後を左右する。土や砂など、異物による汚染が否定できない創があれば、局所麻酔を行い、これでもかというくらい流水で洗浄する必要がある。
破傷風が悪化すると、数週間〜数カ月のICU治療を要することもある。有限な医療資源をさらに有効に活用すべく、小さな努力を積み重ねるべきときである。
薬師寺泰匡(薬師寺慈恵病院院長)[救急医][破傷風]
過去記事の閲覧には有料会員登録(定期購読申し込み)が必要です。
Webコンテンツサービスについて
過去記事はログインした状態でないとご利用いただけません ➡ ログイン画面へ
有料会員として定期購読したい➡ 定期購読申し込み画面へ
本コンテンツ以外のWebコンテンツや電子書籍を知りたい ➡ コンテンツ一覧へ