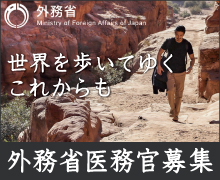お知らせ
岩田健太郎
- 登録日:
- 2020-01-17
- 最終更新日:
- 2025-09-02
「医学部教授を『職能』ベースに」
日本社会は職能ではなく「職名ベース」で仕事を割り振るから、できもしないことをやらされる。医学部教授はその最たるもので、教授選のたびに「臨床、教育、研究面での能力」を査定される。しかし、このすべてに秀でた存在なんて、そうそういるわけではない。加えて、大量の雑用、事務作業をこなし、人事や労務管理、政治活動までこなさねばならない。
大抵の場合、「臨床、教育、研究面での能力に秀でた」は形式的な題目であり、大事なのは研究面だ。ここの査定は非常に厳しく、獲得した研究費や研究業績、将来の発展性まで徹底的に議論される。ところが、臨床、教育面になると、とたんにトーンダウンし「毎週外来をやっているから臨床は大丈夫」とか、「授業を担当しているから教育能力はある」という噴飯ものの「テキトー査定」が行われる。
それでも。往時はそれが「建前である」と了解されていたので、まだ罪は軽かった(よいとは言ってない)。昔は今に比べて奇人変人の教授も多く、その奇行はひとえに「研究能力がぶっとんで高い」ことで許容されてきた。
しかし。現在は診療の質は外的に評価されるため、昔のように「うちの医局ではこうなっている」的な「井の中の蛙」は通用しない。教育面でも学生が教員を評価するため、昔のように「自分の研究を演説するだけ」といった勝手なことはできない。もっとも、その反動で今や学生は大事な「お客様」であり、教育活動はカスタマーサービスだ。先日も某所で「イワタセンセイの授業は上から目線だった」とフィードバックされた。よって翌年からは「誠に僭越ながら、講義をさせて頂きますのでご容赦下さい」と下手(したて)に出ることにしたい(笑)。
嘘と建前では通用しなくなったので、「能力はそこそこでも、全部オールラウンドにできる小粒な官僚タイプ」が増える。が、巨大な研究者は診療も教育も雑用も免責してデカく太く活躍すればよいのだ。その代わり、学生も事務も切り離してハラスメントはさせないようにする。人事権も与えない。教授に何でもやらせる旧態然のやり方では、ジョブ型の組織はできない。研究ゼロの優れた臨床医、教育者も必要だ。
かくいう私もできないこと、苦手なこと、嫌いなことは多い。得意な人に全部アウトソーシングさせてくれたほうが、組織全体のパフォーマンスは必ず高まる。「組織のパフォーマンスが悪くなっても、皆平等に」という昭和なロジックで「みんな沈没」、の悲劇は避けるべきなのだ。
岩田健太郎(神戸大学医学研究科感染治療学分野教授)[医学部教授][能力]
過去記事の閲覧には有料会員登録(定期購読申し込み)が必要です。
Webコンテンツサービスについて
過去記事はログインした状態でないとご利用いただけません ➡ ログイン画面へ
有料会員として定期購読したい➡ 定期購読申し込み画面へ
本コンテンツ以外のWebコンテンツや電子書籍を知りたい ➡ コンテンツ一覧へ