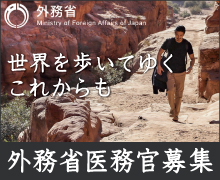お知らせ
岡部信彦
- 登録日:
- 2025-01-16
- 最終更新日:
- 2025-09-17
「GAVIへの資金提供─GAVIってなんだ?」
世界保健機関(WHO)や国際児童基金(UNICEF)は、多くの医療関係者にとって触れることの多い国際組織であろう。しかし、GAVIと聞いてピンとくる方は、ごく少数ではないだろうか。
GAVI(ワクチンと予防接種のための世界同盟)は、“Gavi, the Vaccine Alliance”と名づけられている国際的な官民連携パートナーシップである。GAVIは、予防接種を受ける機会がないためワクチンで予防可能な感染症によって命を落とす子どもたちが多くいる低所得国と、予防接種支援のための出資国、WHO、UNICEF、世界銀行、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、ワクチン業界、研究・技術機関や市民社会団体等をひとつに結びつけることで、子どもたちが予防接種を受ける権利の公平性を高め、世界のワクチンギャップを改善することをめざした活動を行っている。
具体的には、予防接種のための資金調達、支援国に対するワクチン支給、ワクチン市場の形成、予防接種を支える保健システムの強化などである。2000年以降、 GAVIの支援活動によって、延べ5億人以上の子どもたちが予防接種を受け, 700万人以上の命が救われてきたと推計されている。
GAVIの年間予算は約15億ドルであり、米国、英国、ドイツ、フランス、日本、イタリア、カナダ、豪州などが主な資金提供国である。日本は2011年に拠出を開始し、累積拠出額は約265億円(2011〜20年)である。
本誌(No.5285)に、米国のWHO脱退とUSAID(米国国際開発庁)の大幅な縮小・解体などによる医療への影響を憂える一文が、榎木英介氏によって寄稿されていた。筆者が関わっているWHOのポリオ根絶活動も、既に人材・資金の縮小が始まっている。ポリオ会議の縮小、アフリカにおけるサーベイランス・ポリオ検査・ワクチン接種の縮小など、その影響は非常に大きい。GAVIのサニア・ニシュタール最高経営責任者は、米国の年間約3億ドルの資金拠出は不可欠だとして、「米国の支援が得られなければ、はしかやジフテリアのような致命的な病気に対して無防備な子どもたちが120万人死亡することになる」と警告している。
そのような中、石破首相は、日本政府として今後5年間で最大で5億5000万ドル(約812億円)をGAVIに拠出する考えを、来日中のビル・ゲイツ氏に伝えたと報道された。しかし、これに対してネット上では、「税金は日本人のために使え」「発展途上国を支援する余裕などない」といった批判が上がった。
私は、日本は世界の中で高所得国に位置し、平和に過ごすことができる国だと感じている。米国の支援が著しく低下している今こそ、予防接種を受ける機会がないためワクチンで予防可能な感染症によって命を落とす子どもたちを1人でも救うことができるよう、わが国が国際的な支援・貢献を高めるときではないかと思う。
岡部信彦(川崎市立多摩病院小児科)[GAVI][ワクチン][予防接種]
過去記事の閲覧には有料会員登録(定期購読申し込み)が必要です。
Webコンテンツサービスについて
過去記事はログインした状態でないとご利用いただけません ➡ ログイン画面へ
有料会員として定期購読したい➡ 定期購読申し込み画面へ
本コンテンツ以外のWebコンテンツや電子書籍を知りたい ➡ コンテンツ一覧へ