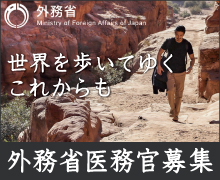お知らせ
宮岡 等
- 登録日:
- 2025-08-08
- 最終更新日:
- 2025-09-09
「うつ病診療の混乱」
1980年代半ばまでの精神医学教育では、多少乱暴な言い方になるかもしれないが、「身体に原因の見いだされないうつ状態」には、「内因性うつ病」と「神経症性うつ病(抑うつ神経症)」があり、これに「反応性うつ病」という分類を加えることもあった。内因性うつ病には、「生まれながらの素因、特有の性格傾向、抗うつ薬が有効、挿話性の経過、長くても2年以内に寛解」などの特徴があるとされていた。一方で、神経症性うつ病では、「性格の脆弱性、様々な程度のストレス負荷、抗うつ薬の有効性は乏しく経過は遷延しやすい」といった特徴があるとされていた。
反応性うつ病は、比較的大きなストレス負荷がみられ、うつ状態の症状やその程度をストレスで説明することができ、その負荷がなくなれば軽快すると考えられた。現在で言えば、「適応障害の人のうつ状態」が最も近い。しかし、診断の際、「そのうつ状態の症状や程度を本当にストレスで説明することができるのか」が、今日の適応障害よりも厳密に議論されていたように思う。
1980年に米国精神医学会からDSM-Ⅲという精神疾患の新しい診断基準が公表され、事態は一変した。大まかにいえばevidence-basedな研究で検証されない診断基準や、国際的な研究で用いることのできない基準は使うべきではないなど、いま考えると多少極端な理由で、各国で独自に用いられていた診断は姿を消すことになった。この流れも関係して、日本生まれではないにしても、国際的とは言えない「内因性うつ病」と「神経症性うつ病」という分類は消え、DSMにならって抑うつの重症度と持続期間によって、うつ病が分類されることが多くなった。
その結果、日本の臨床においても、うつ状態の症状や程度とストレスの因果関係や病前の性格傾向を議論する、すなわち内因性うつ病か神経症性うつ病かを検討する機会は減り、精神科医のうつ状態への対応方法は混乱し、転帰の予測も弱くなった。また、うつ病に対する不適切な薬物療法がしばしば問題とされるが、これも抗うつ薬が有効なうつ病と有効性に乏しいうつ病を区別する視点が乏しくなったため、意味のない抗うつ薬や新薬の使用が増え、それにつけ込んで製薬企業が非科学的に薬を勧め続けていることが一因かもしれないと考える。
それでも1980年代以前の教育を受けた精神科医の中には、DSMに基づいて診断するにしても、「内因性うつ病」と「神経症性うつ病」という分類を頭の隅に置いて鑑別している者がいることは救いであると言えるかもしれない。しかし、その後に精神科医となった医師の中には、内因性うつ病、神経症性うつ病という言葉は知っていても、臨床での意味や意義を理解していない者も多い。国際的な共同研究や生物学的な研究にはDSMのような操作的といわれる診断基準を用いるとしても、臨床現場でどのような手順で治療を進めていくべきかは、改めて考えてよい問題だと思う。
「精神疾患の診断自体にたいした意味はない」という意見は別の場で十分に議論する必要がある。しかし、少なくとも臨床家はDSM、「内因性うつ病、神経症性うつ病」の両者を考慮して、今の精神医療に必要な診断、治療の技術を身につける必要がある。このままでは、うつ病、特に軽症から中等症のうつ病に対する不適切な医療が続いていくことを危惧している。
宮岡 等(北里大学名誉教授)[うつ病][抗うつ薬][内因性うつ病]
過去記事の閲覧には有料会員登録(定期購読申し込み)が必要です。
Webコンテンツサービスについて
過去記事はログインした状態でないとご利用いただけません ➡ ログイン画面へ
有料会員として定期購読したい➡ 定期購読申し込み画面へ
本コンテンツ以外のWebコンテンツや電子書籍を知りたい ➡ コンテンツ一覧へ